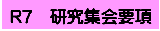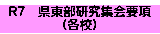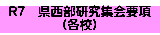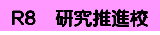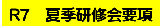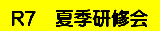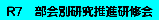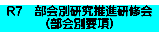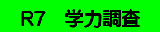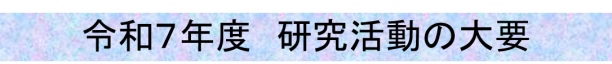

子供の生きる力を育むため、専門職としての資質と指導力の向上を目指す。
1 研 究 の 目 的
教育課程改善の趣旨を踏まえ、豊かな人間性をもち、主体的に学び続ける子どもを育成するために必要な教育内容や教育方法を明らかにする。教育実践活動を通して研究し、会員一人一人が確かな手応えを実感できる研究活動を推進する。
2 研 究 推 進 の 基 本 姿 勢
「一人一人を見つめ育てる」ことを研究推進の基本とする。指導に当たっては、一人一人のものの見方、考え方、感じ方等を大切にし、他とのつながりを見つめる。また、一人一人の活動や学習の軌跡を継続的に把握し、個に応じた指導の手立てを講ずる。
この基本姿勢の下、「実践資料を持ち寄り、子供の姿で語ろう」を合い言葉とし、自らの学びをつくり上げる子供の育成を目指す研究を推進する。
この基本姿勢の下、「実践資料を持ち寄り、子供の姿で語ろう」を合い言葉とし、自らの学びをつくり上げる子供の育成を目指す研究を推進する。
3 研 究 主 題
「自らの学びをつくり上げる子供の育成~主体的・対話的で深い学びを通して~」
4 研 究 主 題 設 定 の 趣 旨
少子高齢化による社会構造の変化、グローバル化の進展や絶え間ない技術革新、人工知能(AI)の飛躍的進歩等、子供たちを取り巻く環境は大きく変化している。このような予測が困難な時代に、子供たちが様々な変化に積極的に向き合い、一人一人が持続可能な社会の担い手として、未来社会を切り拓くための資質・能力を一層確実に育むことが求められている。
本研究会では、平成24年度から教材や人との豊かな関わりを通して、確かな学力・豊かな人間性・たくましく生きるための健康や体力、即ち「生きる力」を子供たちに育むべく、研究を進めてきた。令和2年度からは「主体的・対話的に探究し、確かな学びをつくり上げる子供の育成」という研究主題の下、子供にとっての関わりの対象を幅広く捉え、学びの過程を一層充実させることを目指して研究に取り組んできた。
予測が困難なこれからの時代には、自分で考え、自分で答えを見いだしていく能力が求められる。そこで、今までの研究の積み重ねを大切にしながら、さらに、課題意識を高め、自己調整しながら学習を進める子供の育成を目指し、令和7年度からの研究主題を「自らの学びをつくり上げる子供の育成~主体的・対話的で深い学びを通して~」とする。
「自らの学びをつくり上げる」とは、子供が課題に主体的に向き合い、その解決に向けて必要となる基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得し、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら知識を相互に関連付けたり、仲間と学び合い、確かめ合いながらその解決策を考えたりすることである。すなわち、教材や題材、人や自然、社会等、様々な事象や対象との対話、更には自分との対話を通して、自らを起点とする思いや考えを基に、学びを創出していくことである。
そのために教師は、子供たち一人一人の実態を基に、これまで以上に子供の学びの過程を丁寧に捉えることはもとより、子供たちが学び合いを通して仲間との信頼関係を構築し、様々なつながりを広げ、深めていく状況を的確に捉えて支援したり、一人一人の個性に応じた多様で質の高い学びを目指して学習方法や指導方法を工夫したりしていく必要がある。
本年度、主体的・対話的で深い学びの視点から授業改善を図ることで、子供一人一人が自らの学びをつくり上げながら、実社会や実生活の中でも活用していくことができるように各教科等において「子供の姿を基にした実践研究」に取り組み、主題の解明を図ることとする。
本研究会では、平成24年度から教材や人との豊かな関わりを通して、確かな学力・豊かな人間性・たくましく生きるための健康や体力、即ち「生きる力」を子供たちに育むべく、研究を進めてきた。令和2年度からは「主体的・対話的に探究し、確かな学びをつくり上げる子供の育成」という研究主題の下、子供にとっての関わりの対象を幅広く捉え、学びの過程を一層充実させることを目指して研究に取り組んできた。
予測が困難なこれからの時代には、自分で考え、自分で答えを見いだしていく能力が求められる。そこで、今までの研究の積み重ねを大切にしながら、さらに、課題意識を高め、自己調整しながら学習を進める子供の育成を目指し、令和7年度からの研究主題を「自らの学びをつくり上げる子供の育成~主体的・対話的で深い学びを通して~」とする。
「自らの学びをつくり上げる」とは、子供が課題に主体的に向き合い、その解決に向けて必要となる基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得し、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら知識を相互に関連付けたり、仲間と学び合い、確かめ合いながらその解決策を考えたりすることである。すなわち、教材や題材、人や自然、社会等、様々な事象や対象との対話、更には自分との対話を通して、自らを起点とする思いや考えを基に、学びを創出していくことである。
そのために教師は、子供たち一人一人の実態を基に、これまで以上に子供の学びの過程を丁寧に捉えることはもとより、子供たちが学び合いを通して仲間との信頼関係を構築し、様々なつながりを広げ、深めていく状況を的確に捉えて支援したり、一人一人の個性に応じた多様で質の高い学びを目指して学習方法や指導方法を工夫したりしていく必要がある。
本年度、主体的・対話的で深い学びの視点から授業改善を図ることで、子供一人一人が自らの学びをつくり上げながら、実社会や実生活の中でも活用していくことができるように各教科等において「子供の姿を基にした実践研究」に取り組み、主題の解明を図ることとする。
5 研 究 内 容
(1) 教材研究と単元構想
子供は、授業を通して自分を取り巻く自然、文化、社会、人等と豊かに関わり、基礎的・基本的な知識及び技能を身に付けるとともに、それらを活用して思考力、判断力、表現力等の力を伸ばしていく。また、学びに向かう力、人間性等は、生きて働く知識及び技能の習得や未知の状況にも対応できる思考力、判断力、表現力等の育成を方向づける重要な要素である。そうした資質・能力を育成するための手立てとして、十分な教材研究と単元構想の工夫が不可欠である。
個自らの学びをつくり上げていくためには、課題意識や探究への意欲を生む教材であることが大切である。既に教材としてつくられている場合は教材解釈、ある素材から教材にしていく場合は教材開発として取り組み、子供と教材との関わりを究明する。
教科・領域等における単元(題材)とは、教科の内容や子供の学習経験を一つのまとまりのあるものとして捉え、それを学年や教科の指導計画の単位として考えたものである。単元構想では、子供の実態把握の上に立ち、学習指導要領の目標と内容を理解し、教材の分析に努める。その展開では、学習課題を吟味し問題追究の方向に沿って必然性と連続性をもたせることが大切である。
また、教科間等のつながりを踏まえた教材研究と単元構想により、幅広い学習や生活場面で活用できる力が子供たち一人一人に育成される。
(2) 学習過程の工夫
授業においては、どの子供も知的好奇心や追究意欲をもって主体的に取り組むことのできる学習過程を工夫したい。学習課題や問題をもつ過程においては、子供にとって身近なものや生活経験を想起させるもの等を提示し、子供が自ら学習課題や問題を見付けることができるように工夫する。その際、学習課題や問題が教科や単元のねらいに迫っていくもの、子供にとって必要感のあるものになっていることが大切である。
学習課題を解決する過程においては、子供一人一人が解決の見通しをもって学習に取り組むことができるように工夫する。また、集団での学び合いの場を効果的に位置付け、他の意見や考えから気付きを得たり、自己の学習活動を振り返って更に自分の考えや思いを広げたり深めたりできるようにする。そのため、学習活動では、授業のねらいに応じて、観察・実験や見学、調査等、体験的な活動を通して学ぶこと、自らの考えをまとめることや発表すること、グループや全体で考え、協力し合う活動を取り入れること等を大切にする。
授業の展開においては、教師は子供一人一人の学びを保障し、自他との関わりを通して個の学びが高まるよう指導し働きかけていく必要がある。そうした授業により、子供は教科の見方・考え方を働かせながら資質・能力を身に付け、自らの学びをつくり上げていく。
また、子供や学校等の実態、各教科等の特質や学習過程を踏まえ、子供が学習の進め方を自己決定し、それを共有することで、自らの学び方を調整する個別最適な学びや協働的な学びのツールの一つとしてICTを効果的に活用し、授業改善につなげることも重要である。授業者がICTの必要性を理解し、その利便性を十分に活用していくために、資質・能力の育成や各教科等の特質、限られた学習時間の効率的な運用等の視点をもつことも大切である。
(3) 指導と評価の一体化
指導における目標と、評価の目標・規準は、表裏一体となっていなければならない。評価の3観点(「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」)を基に、指導に際しては、いつまでに何をどのように全ての子供に実現させるのかという明確な見通しが必要であり、評価に際しては、どの程度達成されているかという視点から、一人一人の子供の姿を見つめなくてはならない。
子供が自らの学びをつくり上げるためには、子供一人一人がそれまでの学習で身に付けている力を教師が的確に把握することが不可欠である。学習の状況、各種学力調査での状況等を踏まえて指導するとともに、知識及び技能に加え、思考力、判断力、表現力等が一体となり、どのように身に付いているのかを評価する。そして、学びの成果として「自分にどのような力が身に付いたか」更には、「今後どのような力を身に付けたいか」を、子供自身が客観的に捉えることができる評価を工夫することで、自己肯定感の向上を図ることも大切である。
そのためには、学級経営の中でどの子供も尊重されていることが基盤にあり、他者との比較ではなく、一人一人のよさや可能性を多様な側面で評価しようとする教師の姿勢が大切である。子供の成長にとって意味ある授業、躍動する授業を基本として、指導と評価の一体化を考え捉えていく。
子供は、授業を通して自分を取り巻く自然、文化、社会、人等と豊かに関わり、基礎的・基本的な知識及び技能を身に付けるとともに、それらを活用して思考力、判断力、表現力等の力を伸ばしていく。また、学びに向かう力、人間性等は、生きて働く知識及び技能の習得や未知の状況にも対応できる思考力、判断力、表現力等の育成を方向づける重要な要素である。そうした資質・能力を育成するための手立てとして、十分な教材研究と単元構想の工夫が不可欠である。
個自らの学びをつくり上げていくためには、課題意識や探究への意欲を生む教材であることが大切である。既に教材としてつくられている場合は教材解釈、ある素材から教材にしていく場合は教材開発として取り組み、子供と教材との関わりを究明する。
教科・領域等における単元(題材)とは、教科の内容や子供の学習経験を一つのまとまりのあるものとして捉え、それを学年や教科の指導計画の単位として考えたものである。単元構想では、子供の実態把握の上に立ち、学習指導要領の目標と内容を理解し、教材の分析に努める。その展開では、学習課題を吟味し問題追究の方向に沿って必然性と連続性をもたせることが大切である。
また、教科間等のつながりを踏まえた教材研究と単元構想により、幅広い学習や生活場面で活用できる力が子供たち一人一人に育成される。
(2) 学習過程の工夫
授業においては、どの子供も知的好奇心や追究意欲をもって主体的に取り組むことのできる学習過程を工夫したい。学習課題や問題をもつ過程においては、子供にとって身近なものや生活経験を想起させるもの等を提示し、子供が自ら学習課題や問題を見付けることができるように工夫する。その際、学習課題や問題が教科や単元のねらいに迫っていくもの、子供にとって必要感のあるものになっていることが大切である。
学習課題を解決する過程においては、子供一人一人が解決の見通しをもって学習に取り組むことができるように工夫する。また、集団での学び合いの場を効果的に位置付け、他の意見や考えから気付きを得たり、自己の学習活動を振り返って更に自分の考えや思いを広げたり深めたりできるようにする。そのため、学習活動では、授業のねらいに応じて、観察・実験や見学、調査等、体験的な活動を通して学ぶこと、自らの考えをまとめることや発表すること、グループや全体で考え、協力し合う活動を取り入れること等を大切にする。
授業の展開においては、教師は子供一人一人の学びを保障し、自他との関わりを通して個の学びが高まるよう指導し働きかけていく必要がある。そうした授業により、子供は教科の見方・考え方を働かせながら資質・能力を身に付け、自らの学びをつくり上げていく。
また、子供や学校等の実態、各教科等の特質や学習過程を踏まえ、子供が学習の進め方を自己決定し、それを共有することで、自らの学び方を調整する個別最適な学びや協働的な学びのツールの一つとしてICTを効果的に活用し、授業改善につなげることも重要である。授業者がICTの必要性を理解し、その利便性を十分に活用していくために、資質・能力の育成や各教科等の特質、限られた学習時間の効率的な運用等の視点をもつことも大切である。
(3) 指導と評価の一体化
指導における目標と、評価の目標・規準は、表裏一体となっていなければならない。評価の3観点(「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」)を基に、指導に際しては、いつまでに何をどのように全ての子供に実現させるのかという明確な見通しが必要であり、評価に際しては、どの程度達成されているかという視点から、一人一人の子供の姿を見つめなくてはならない。
子供が自らの学びをつくり上げるためには、子供一人一人がそれまでの学習で身に付けている力を教師が的確に把握することが不可欠である。学習の状況、各種学力調査での状況等を踏まえて指導するとともに、知識及び技能に加え、思考力、判断力、表現力等が一体となり、どのように身に付いているのかを評価する。そして、学びの成果として「自分にどのような力が身に付いたか」更には、「今後どのような力を身に付けたいか」を、子供自身が客観的に捉えることができる評価を工夫することで、自己肯定感の向上を図ることも大切である。
そのためには、学級経営の中でどの子供も尊重されていることが基盤にあり、他者との比較ではなく、一人一人のよさや可能性を多様な側面で評価しようとする教師の姿勢が大切である。子供の成長にとって意味ある授業、躍動する授業を基本として、指導と評価の一体化を考え捉えていく。
6 研 究 を 進 め る に 当 た っ て
(1) 研究の焦点化
① 「生きる力」を育むため、学習指導要領との関連を図る。
② 研究の趣旨やねらい、研究仮説を明確化する。
③ 研究専門委員会や学力調査委員会、研究推進校等、各組織間相互の緊密な連携を図る。
④ 指導と評価の一体化を目指し、研究主題や研究内容と研究活動、そして学力調査活動との関係を
重視する。
(2) 研究を進めるに当たっての留意事項
① ブロック小教研(以下、「ブロック」と記す)の活発な研究活動を基盤にして推進する。
② 会員一人一人がブロックの研究のねらい及び方法を把握し、自主的な研究を行うように配慮する。
③ 研究のための会合等を精選し、運営の効率化を図る。
④ 県教育委員会、市長村教育委員会、研究諸機関、諸団体との連携を図り、研究を進める。
⑤ 研究推進校の指定に当たっては、原則として各教科等部会の研究推進の中核となるブロックを、
東西から1ブロックずつ2年間のサイクルで指定する。その指定したブロックの推薦に基づき、研
究推進校を決定する。そして、その研究推進校の研究に対して、ブロックや県の各教科等部会が
研究活動や運営に全面的な支援をする。
① 「生きる力」を育むため、学習指導要領との関連を図る。
② 研究の趣旨やねらい、研究仮説を明確化する。
③ 研究専門委員会や学力調査委員会、研究推進校等、各組織間相互の緊密な連携を図る。
④ 指導と評価の一体化を目指し、研究主題や研究内容と研究活動、そして学力調査活動との関係を
重視する。
(2) 研究を進めるに当たっての留意事項
① ブロック小教研(以下、「ブロック」と記す)の活発な研究活動を基盤にして推進する。
② 会員一人一人がブロックの研究のねらい及び方法を把握し、自主的な研究を行うように配慮する。
③ 研究のための会合等を精選し、運営の効率化を図る。
④ 県教育委員会、市長村教育委員会、研究諸機関、諸団体との連携を図り、研究を進める。
⑤ 研究推進校の指定に当たっては、原則として各教科等部会の研究推進の中核となるブロックを、
東西から1ブロックずつ2年間のサイクルで指定する。その指定したブロックの推薦に基づき、研
究推進校を決定する。そして、その研究推進校の研究に対して、ブロックや県の各教科等部会が
研究活動や運営に全面的な支援をする。
.